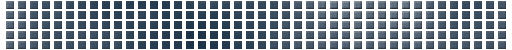
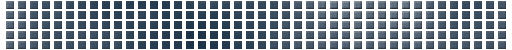
昭和10年夏頃航空本部長山本五十六中将、技術部長原五郎中将、技術部主席部員和田操大佐を中心に将来の航空機武装について熱心に検討されていたが、たまたま在仏武官からエリコンの20ミリ機銃の報告が入り、調査した結果優秀な機銃と認められた。
一方国内では陸軍の管理工場の日本特殊鋼株式会社で河村正弥博士を中心に機関砲の開発が進められ、20ミリ級の機関砲(陸軍は20ミリ以上を機関砲と呼んでいた。)の試作成功も伝えられていたが、陸軍の管理工場に海軍が係われば、陸海軍の摩擦を生じかねず、またこの機関砲が実用化されるまでには問題が生じる可能性も有ったので、エリコンの20ミリ機銃を全面的に採用する事に決定した。
しかしエリコンの20ミリ機銃を海軍工廠で生産する余裕は無かった。対米戦の風雲急を告げる中、昭和10年やっと横須賀海軍工廠の機銃工場を完成させ、機銃の生産を呉海軍工廠から横須賀海軍工廠に移管し、毘式7.7ミリ機銃の生産がやっと軌道に乗りつつあった。この様な状況ではとても7.7ミリ機銃に加えて20ミリ機銃の生産まで海軍工廠で開始することは出来なかった。かと言って将来航空機の武装の主力となるような機銃を全面輸入に頼ることも許されなかった。主力戦闘機の機銃を全面輸入していたら、本格的な対米戦争が勃発して武器の輸入が不可能になったら、主力戦闘機に搭載する機銃が無くなってしまうではないか。
この時民間での国産化の話を最初に持ち込まれた民間の雄三菱重工は、海軍工廠と同じように設備の大拡張中で余裕が無く、機銃生産への参画を断った。航空本部技術部長原五郎中将は山下汽船の山下亀三郎氏に相談し、そして其の話が浦賀船渠の寺島健氏にもたらされたれたのは昭和11年正月のことであった。当時海軍航空本部と浦賀船渠との間で次のような約束が交わされて、ついに富岡兵器製作所が設立された。
「機銃に関する技術の導入及びその生産は会社のリスクで実施する。但し約束の時期までに要求する性能の機銃が約束の数だけ出来たならば海軍で買い上げる。生産計画は以下の通り。後に年に1万挺近くまで達することを思えば、その数の少なさは驚くばかりである。 」
機銃 昭和12年 60挺 昭和13−16年 年100挺 弾薬包 昭和12年 5万発 昭和13−16年 年10万発
エリコン機銃の各型
浦賀船渠が製造販売権を取得したエリコンの20ミリ機銃には初速600m/s,重量23kgのFF型、装薬量と銃身長をFF型より50%増して、初速を750m/sに増した重量30kgのFFL型,さらに装薬量と銃身長をFF型の約2倍にして初速を900m/sまで増加させた重量39kgのFFS型の3種があった。ただし初速には3段階あるが、発射される弾丸自体はFF,FFL,FFSとも同一である。
エリコンの20mm機銃には、これら3種の他にもヒスパノスイザ社とエリコン社が共同開発したモーターカノン型式のFFS(MK)もあった。モーターカノンは機銃が航空機の中で最も剛性が大きいエンジンに直接固定され、機体の中心軸上にあるプロペラボスを通して発射されるため命中率が良くなる特徴があった。また剛性の大きいエンジンに固定出来るため威力のある弾丸が使用できるという利点がある型式であった。このモーターカノンが浦賀船渠が得た権利の範囲内であったか否かは、製造販売権の譲渡契約書の一部が現存するものの明確でない。
従来戦闘機に装備されていた7.7ミリ機銃はわずかに13.3kgであったから、ただでさえ重い20mm機銃はFF型が戦闘機の両翼に装備できる限界と思われ、まずFF型が国産された。富岡兵器製作所は、昭和12年6月には輸入材料を加工したエリコンFF型固定機銃を完成させ、昭和14年7月には国産材料を用いたFF型固定機銃の純国産銃も完成した。
このエリコンFF型固定機銃はまず「恵式20ミリ固定機銃1型」と名付けられて採用され、続いて昭和16年12月13日「99式1号20ミリ固定機銃」と名称が変更された。この間に富岡兵器製作所は、13年7月1日、浦賀船渠から独立して大日本兵器株式会社となっている。
航空機への搭載
機銃の国産化が進む中、航空機搭載の実験も繰り返し行われた。昭和13年8月95式艦戦(FF型2挺),96艦戦(FF型2挺),ドヴァチン戦闘機(ヒスパノスイザモーターカノン1挺)の比較空中実験が計画されるが、95式艦戦のFF型2挺の翼内装備は翼断面のフクラミが大きすぎて、ほとんど実験出来ずに中止された。
96艦戦のFF型2挺は総合成績最良と認められたが、命中精度はモーターカノンを搭載したドヴァチン戦闘機が最良であった。その後、機銃自体は国産化できる所まで試作が進んでいたが、日本海軍にはモーターカノンの装備に適するエンジン(プロペラシャフトが中空なエンジン)がなく、結局終戦まで採用されずに終わっている。
FF型は、引き続いて昭和14年1月樺太内路にて耐寒実験、同年7月96艦戦の翼内装備FF型2挺の実用実験、15年6月零式艦上戦闘機装備空中実験と進められ、零戦の空中実験の結果、空気装填弁類の強化が図られる。そして同年7月FF型を装備した零戦が中支に進出、同年8月遂に重慶上空にて大戦果を納めたのである。
100発入弾倉の開発
エリコンの20ミリ機銃の1番の問題点は携行弾数の少なさであった。1発当たれば戦闘機ならバラバラになると言われた20ミリ機銃も、各銃にたった60発しか搭載出来ないのは問題であった。昭和16年2月より100個入りと120個入りの弾倉の設計を開始、同年7月には試作が完成し地上実験が開始された。120個入り弾倉は余りにも重すぎてハンドリングできず、地上実験のみで研究は打ち切られる。
同年8月、空中荷重実験が開始され給弾力向上のためバネは弾倉の前後に取り付けられた。また弾倉の重量で機銃がねじられて給弾不良や不発を生じる事が判明し、給弾口部に弾倉の重量を支える支柱を付け、弾倉本体も釣上げる構造として、機銃に弾倉の重量の影響が直接かからないように改良された。
*2昭和16年11月に100発入り弾倉の実験は全て終了し採用が決定する。100発入り弾倉は従来の60発入り弾倉より高さが120ミリ大きかったから、この弾倉を装備した零戦の翼は上下両面が写真の様に膨らんでいたが、見にくい位置なので識別は容易では無い。
100発入り弾倉は昭和17年7月頃から本格的に量産に入り、同年11月から12月頃60発入り弾倉の生産数を越えたものと推定される。ちなみに同年11月の60発入りと100発入りの弾倉の月間生産数量は各400個であった。*3100発入り弾倉は1号固定機銃3型にのみ採用されたとする文献が多いが、昭和19年3月に海軍航空本部が発行した飛行長主管兵器説明資料によると1号固定機銃2型改2の弾倉は60,100発入の両方が使えることになっているから、2型にも使えたのは明らかである。
この弾倉は99式20ミリ1号固定機銃2型や3型と組み合わされて、零戦32型が就役する頃から続々と零戦に装備され、ソロモンの空の激闘に参加する事になる。
そして紫電11型の最初の武装はこの100発弾倉を付けた99式20ミリ1号固定機銃3型4門であった。甲,乙,丙等の派生型を除く純粋な紫電11型にしか99式20ミリ1号固定機銃3型は搭載されていないが、約300機が生産されたとされている紫電11型の写真、即ち99式20ミリ1号固定機銃3型を搭載した紫電の写真は、これまで1枚も見たことが無い。御存知(お持ち)の方はお知らせいただきたい。
2号銃への転換
99式20ミリ1号固定機銃の次の欠点は、初速が600m/sと低いため弾丸の低下量が大きいことであった。500mでの弾丸の低下量は、毘式7.7ミリ機銃が290センチなのに対し、1号銃は490センチもあった。
これでは威力があっても何々当たらない。ただし初速の速く弾丸の直進性が良い恵式20ミリ2号固定機銃の重量は、1号銃の23kgに対して30kgもあり、かつ発射反動も大きい。このためこのため2号銃は1号銃の試作完了後に試作が開始された。
昭和15年7月に試作(見取設計)を開始し、16年9月完成、同年11月には試験を終了していたが、部隊からは搭載すれば運動性が悪くなると歓迎されず、舶着機銃が恵式二十粍2号固定機銃と呼ばれていたものの、開戦1ケ月前にやっと国産機銃の性能試験が終了し、量産の手配が開始された状況であった。
ところが太平洋戦争に突入すると、B17の防御が堅く、99式20ミリ1号固定機銃では威力不足と認識され、かつ敵のブローニング機銃の弾丸の直進性が良い事などから、2号銃の採用が決定し、昭和17年7月22日、99式20ミリ2号固定機銃2型と呼ばれる事になり量産が開始された。
この機銃を搭載した最初の零戦は同年8月末3機に部隊に引き渡され、爾後逐次増加し同年10月末までに30機が引き渡される計画であった。
*4 機銃製造の重点は昭和17年夏頃から、1号銃から徐々に2号銃にシフトして行ったが、そのテンポは遅く昭和18年末でも2号銃の生産数は1号銃より少なかった。このため同年末から就役し始めた20ミリ機銃4挺装備の雷電21型,31型,33型の各型は1号銃2挺と2号銃2挺の変則的な装備を採用せざるを得なかったと伝えられる。
99式20ミリ2号固定機銃は2型から生産が開始されたが、2型はごく初期に少数が生産されたに過ぎないと推定され、2号銃の生産の主力は100発弾倉を用い、空気発射から電気発射に改良された99式20ミリ2号固定機銃3型であった。この3型が太平洋戦争中期以降に活躍した全ての単座戦闘機に搭載された。
即ち零戦22型甲,52型,雷電11型の各戦闘機である。紫電では、この機銃を4門搭載した型が、紫電11型甲と呼称され、フィリピンに出撃した341空や201空の補充機などがこの紫電11型甲であった。
ベルト給弾化(4型の開発)
一方携行弾数の増加のため、ベルト給弾の研究も昭和16年10月にスタートしていた。100発入り弾倉の試験が佳境を迎えていた頃の事である。そして太平洋戦争が開戦すると携行弾数の増加の声は一気に高まった。この時ベルト給弾の方法として3種類が考案されかつ試作された。
1.機銃の前進,後退運動を利用してスプロケットホイールを回転させて弾帯を送り込む方式(イギリスのイスパノスイザ20mm機銃が採用)この方式は計画のみで終了
2.小型電動機を使ってバネを巻き込む方式試製給弾装置1型と命名され、電気部品を芝浦電気に製作を依頼し、海軍航空技術廠で試作され、室内実験も成功したが重量,容積過大で研究打ち切りとなった。
3.左右の退却板を改造してカムを設けてベルトの給弾を行う方法。挿弾子は日本特殊鋼の河村博士の考案になるもので、結局この方法が採用された。
日本特殊鋼が試作を担当し、昭和17年9月に試作完成、様々な改造が進められつつ、同年12月に地上試験が終了し射撃試験が開始された頃、ベルト給弾式の4型は試験中にもかかわらず各種飛行機に採用されることとなり、背水の陣となった。
空中実験は昼夜兼行で行われ、機銃にも機体にも様々な改造が実施され苦心惨憺の末、昭和18年5月遂に1号機銃の試験が成功し、99式20ミリ1号固定機銃4型と名付られる。そして同年8月には2号銃の試験も成功裏に終了し、99式20ミリ2号固定機銃4型と名付けられた。
1号固定機銃4型は大日本兵器株式会社幸田工場で、2号固定機銃4型は豊川海軍工廠にて量産が開始された。
2号銃は試作完成と同時に量産を開始したため、量産機が18年10月に完成すると、図面の誤記、試作図面訂正の量産図面反映忘れ、公差の不備等が重なり、量産しながらも量産機の改造や図面訂正を繰り返すこととなり大混乱となった。
幸田工場の1号銃も事情はほぼ同じで、昭和19年4月に幸田工場で1号銃の量産銃が完成した際、問題が一気に噴出した。1号銃はもともと2号銃に比べてバランスが悪く、2号銃よりも解決には苦労したが、豊川海軍工廠での経験を生かし約1ケ月の缶詰作業で切り抜けたと言う。この1号固定機銃4型の量産は昭和20年2月に中止され、以降2号固定機銃4型の生産に全力が注がれた。
ベルト給弾式の99式20ミリ1号および2号固定機銃4型は紫電11乙と紫電改の他に零戦52型,雷電21,31,33型と雷電32型の斜銃、月光斜銃などに装備され、太平洋戦争末期の主力機銃となった。また変わった所では、1号固定機銃4型が瑞雲と流星の両翼内に各1挺、計2挺装備されていた。
99式20ミリ1号旋回機銃4型
話は跳ぶが、99式20ミリ1号固定機銃4型はベルト給弾だが、99式20ミリ旋回機銃4型は45発ドラム弾倉を使用し、動力旋回機銃架に搭載用の機銃であり、同じ20ミリ1号機銃でも固定機銃と旋回機銃では型の意味は違っている。発射速度増大装置の開発
(4型の改造)
2号銃は1号銃より初速が速いため、命中率が良く、かつ弾丸の威力も大きかったが、発射速度は1号固定機銃4型の550発に対して2号固定機銃4型は500発と発射速度が低いのが欠点だった。
(弾倉式の2号固定機銃3型は480発であり、ベルト給弾式の方が発射速度は若干早かった。)
この発射速度の低さは、2号銃の本格的採用が始まった時から既に問題になっており、昭和18年8月にも退却長を短縮し、強力な緩衝バネで復帰を速めて発射速度を向上させる、発射速度増大装置の開発計画が持ち上がった。
しかし当時は2号銃の量産を開始したばかりで、2号銃の生産を開始した各工場で初期的な故障が多発して、新装置の開発どころでは無かった。2号銃の量産が本格化して、生産が順調に進み始めた昭和19年5月、懸案の発射速度増大装置の開発がスタートする。同年7月には地上および空中実験が良好な成績で終了し、発射速度は500から620発/分となり、直ちに量産が開始された。
同年8月には硫黄島、サイパン島攻撃に使用、実用実験されたと言う。発射速度増大の代償として反動力が1.5トンに増加し、「機体側の支基に折損を生じ、補給対策実施済のものを生産した。」と記録にあるが、機銃の改造なのか?今ひとつはっきりしない。昭和19年秋以降に完成した戦闘機の20ミリ2号固定機銃4型には、この発射速度増大装置が付けられていたものと推定されるが、根拠文書は未だ発見できずにいる。
2号固定機銃5型の開発
99式20ミリ固定機銃4型の後継として開発された4型の発射速度増大型である。4型の発射速度は発射速度増大装置の付加により、従来500発/分から620発/分に改善されたが、更なる向上を目指して4型の退却部の重量を更に1kg程度軽減し、増速バネを強力にしたもので、発射速度は750発/分、重量は38.5kgであった。
昭和19年10月設計着手、同年12月30日、多賀城海軍工廠にて試作銃4挺完成、昭和20年1月には製作図面が完備する。量産図面の完成年月日が今に伝わるのはこの2号固定機銃5型のみである。
4型の量産図面の不備に泣かされ、この5型では量産用図面の整備に相当神経を使ったのが判る。同年5月には多賀城海軍工廠にて第1次増加試作機銃10挺が完成、機能・性能は極めて良好であり、発射速度は720発/毎分となった。
同年7月増加試作銃50挺完成、反動力が4型の発射速度増大装置付の1.5トンに対し、5型では2.5トンとなったため、搭載戦闘機の機体補強計画中に終戦となった。また、烈風の翼内に6挺装備が決定し射撃基礎実験も開始されていた。
99式20ミリ2号固定機銃の後継機種として開発されていた18試20ミリ固定機銃1型が、この機銃の成功によって、開発中止となったため、この99式20ミリ2号固定機銃5型が日本海軍の最後の20ミリ機銃となったのである。
18試20ミリ固定機銃1型
99式20ミリ2号固定機銃の後継機種として開発された初速900m/s,発射速度700発/分,重量45kgの戦闘機用の翼内機銃である。
18試20ミリ固定機銃の弾丸は99式1号固定機銃や2号固定機銃と共通であるが、発射のための装薬は2号銃の21.6gに対して34gと50%以上も多い、このため初速は前者の750m/sから900m/sに増加している。
そのくせ薬莢の長さは2号銃より18試固定機銃の方が3mm短い(装薬の充填密度が高い事を意味する。)と言う、かなり特徴的な弾薬を使用していた。
銃の機構はガス圧利用式で先行して開発されていた、17試30ミリ固定機銃1型(後の5式30ミリ固定機銃1型)のスケールダウン版であった。
昭和18年9月に要求性能が決定され、一技廠に於いて設計・試作が着手された。昭和19年1月1号機が完成、一技廠において直ち実験が開始された。
同年8月には、零戦に依る空中実験を実施する所まで遂にこぎつけたが、他の緊急作業が相次いで発生したためと、同年末には、発射速度が720発/分に達する99式20ミリ2号固定機銃5型が使える目途が立ったため、昭和20年3月頃には試作はほとんど中絶状態となり、開発中止されるに至った。
機銃の作動メカニズム
99式20ミリ機銃の作動方式は、国内ではエリコン方式と呼ばれているが、国際的にはAPI方式(Advanced Primer
Ignition/先進的な火管発火方式)と呼ばれるブローバックの方式の一種である。本来のブローバック方式では、弾薬包は薬室に完全に装填された状態で火管に打撃が加えられて発火し、弾丸が発射される。
しかしAPI方式では弾薬包が薬室に完全に装填されるる直前で発火する。このため尾栓が前進するエネルギーと発射エネルギーが相殺されて、機銃自体が受ける発射反動力が小さくなるので、20ミリという大口径の割には軽量小型化が可能であり、ブローバック方式の中でも優れた方式であった。
例えば陸軍の20ミリ機関砲のホ5は、砲身後座・ガス利用式で85gの弾丸を初速750m/sで発射する機関砲で、重量が37kgもあったが、海軍の99式20ミリ機銃は、ホ5の1.5倍もある123gの弾を初速750m/sで発射するにもかかわらず、機銃の重量は僅かに30kgであった。
99式20ミリ機銃の作動原理は、1号固定機銃も2号固定機銃も基本的には同じである。1図の様に機関部の最後部まで下げられた尾栓は、発射杷柄を引くと2図の様に尾栓懸金が外れて推進バネの力により前進する。
この時、給弾口にある弾薬包は尾栓頭で押されて薬室内に前進する。弾薬包は3図の様に薬室の終端まで装填される前に発火されて弾丸を発射する。尾栓は4図の様に発射反動を吸収しながら、更に薬室終端まで達した後、5図の様に発射反動によって機関部の最後部まで再び後退する。
この尾栓後退途中に爪が出ており、空薬莢が爪に蹴り出されて排出される仕組みであった。尾栓が機関部の最後尾に達した時、発射杷柄が引かれていないと、尾栓は尾栓懸金にかかって停止する。発射杷柄が引かれていると、尾栓懸金は尾栓にかかる位置から外れており、尾栓は停止せずに再び1図に戻って射撃が継続される。
さて1図の状態まで尾栓を下げるにはどうするのか?20ミリ機銃ではこの作動機構を装填機(チャージャー)と言う。実際には尾栓を後退させて装填準備をするだけで、装填を直接行う機構では無い。1−4図では省略していた装填機の概念を追加したのが6図と7図である。
尾栓は推進バネを収納するケースと一体になっているので、尾栓を後退させる為には、推進バネを縮めなければならない。この推進バネ力のみで発射の反動を受けた尾栓の後退を止め、その反発力のみで装填を行うのだから、推進バネ力は相当なもので、装填機のシリンダーの力で縮められるのである。
当初は空気でシリンダーを作動させる方式であったが、当時の技術力では空気の漏れを完全に止めるシール部が製造出来ず、漏れが時々発生し空中で装填,抜弾が出来なくなるという不具合が根絶出来なかかったため、1号20ミリ固定機銃3型の途中から油圧方式に変更されている。(油圧式装填機の試験完了は、17年8月)
図6,7は装填機構説明用概念図であり、実際の取付位置は、固定機銃では全て機銃の左側面に、1号20ミリ旋回機銃4型では銃身の上、且つ固定機銃よりかなり前方に装着されている。
弾薬
99式20ミリ機銃の弾薬は、1号固定機銃用を99式(当初は恵式)20ミリ機銃1号弾薬包、2号固定機銃用を99式(当初は恵式)20ミリ機銃2号弾薬包と呼称した。1号弾薬包と2号弾薬包は弾丸は共通となっており、2号弾薬包は初速を速くするために装薬を1号弾薬包の13.6グラムから21.6グラムに増加させている。このため2号弾薬包の長さは1号弾薬包より29.5ミリ長い173.9ミリになっている。話は飛ぶが、薬莢を含む弾薬全体の事を海軍は弾薬包、陸軍は弾薬筒と別の呼び方で呼んでいる。
弾薬包の種類は大別すると7種類あり、1号銃用の弾薬包は1号XXX弾薬包と呼ばれていた。一例を示せば通常弾は1号通常弾薬包と呼称される。
実戦の場合、4種類の弾種を一定のサイクルで混ぜて用いた。
通常弾薬包(錆):破壊用
曳跟通常弾薬包(赤):弾道修正/破壊用
焼夷通常弾薬包(黄):ガソリンタンク着火用
徹甲通常弾薬包(白):貫徹・破壊用
( )で示したのは、弾種の識別のための弾丸外側の塗色=識別色である。弾帯に着けられた弾は、一定の法則で装填されるので、錆,赤,黄,白,錆,赤,黄,白というように一定のリズムでカラフルに見えるのである。
弾薬包は上記の種類は同じであっても信管の違いや弾丸の内部構造の違いによって更に細分されており、塗色の上に書かれる白線の数や太さで判別される。
例えば写真358Cの、通常弾薬包は弾丸の塗色は錆色であり、その上に白線が2本書かれていることから1号通常弾薬包改2と識別できる。私は未だ錆色という色がどんな色か知らないので、もし知っている方がいらっしゃったら教えていただきたい。
この写真は米軍によって捕獲された弾薬包の写真で、英文の解説が付いているが、その解説に色はライトグリーンとあるので銅の錆の色の緑青色に近いのではないかと想像してはいるのだが、曳跟通常弾薬包は弾道を修正するために、3秒間曳跟を視認出来、その間1号弾薬包で1,000メートル,2号弾薬包で1,300メートル曳跟を引きながら飛翔する。焔の色は赤,橙,黄色の3色があった。赤は蓚酸ストロンチウム,過酸化ストロンチウムで発光、橙は塩化ナトリウム,過酸化カルシウム,炭酸カルシウムで、黄色は硝酸バリウムと蓚酸ソーダで発光させていた。
徹甲通常弾薬包は敵機の装甲部やエンジン等の堅固な部分の破壊を狙った弾で、その威力は、B17の操縦席の装甲に相当する15.6ミリの防弾鋼板を1号弾薬包なら200メートルで、2号弾薬包なら300メートルで貫通できた。それまで用いられていた97式7.7ミリ機銃の撤甲弾薬包は射距離100メートルで、僅か8ミリの防弾鋼板しか貫通できなかったから格段の進歩であった。
実戦に使われた弾にはもう一種類、着色弾薬包がある。海面に打ち込んで、発見した潜水艦の位置を表示するために造られた弾であり、戦闘機には搭載されていない。
残りの2種は訓練や試験の時に使用される演習弾薬包(識別色/黒)と曳跟弾薬包(識別/赤)である。両弾種共炸裂する必要はなく、弾丸の中には炸薬が入っていないので、標的に衝突しても爆発しない。吹き流しを射つ時には、実戦と同様に一定の割合で弾帯(弾倉)に込められた曳跟弾の曳跟で射線を確認しながら狙いを調整する訓練をするのである。
初期の機械式信管
弾丸の中に炸薬が入っていても、目標に当たった時に信管が確実に炸裂してくれなければ意味が無い。エリコンの20mm機銃導入時の信管は機械式で通常弾薬包や曳跟通常弾薬包、焼夷通常弾等の機体破壊用の弾種は機体に接触した瞬間に発火させるため弾頭信管であった。
他にもガソリンタンク発火用の遅動炸裂徹甲弾薬包用の弾底信管も有ったが、この弾が国産されたか否かは不明である。
弾頭信管は通常弾薬包用,曳跟通常弾薬包用、焼夷通常弾用では細部に違いがあるが、基本的な発火機構は何れも同じで、弾丸の頭部の信管が敵に接触し、信管頭部が潰れると同時に釘の様な形をした打針は信管内に突入して雷管を叩き、厚さ0.05ミリの錫箔の中に入った発薬(0.1g)を発火させ、発薬の下にある窒化鉛、その回りのペントリットが順に発火し、弾丸内の炸薬を発火させる仕組である。
信管には安全装置が2重に組まれており、打針は安全栓で止められており、これが外れないと打針は動かず、発火しない仕組みであった。
この安全栓は安全留金で止められているが、発射の衝撃で安全留金が留金発條(バネ)を圧縮して安全留金が安全栓から外れ、安全栓が動ける様になり、次に安全栓は弾丸の回転によって打針から外れる仕組であった。
即ち信管は発射の衝撃と弾が回転が加えられない限り爆発しない2重の安全機構が組まれていたのである。この信管は当時としては非常に良く出来た信管であった。
しかし20ミリ機銃はよく腔発を起こし、そのほとんどが信管の不具合と考えられた。この信管の欠点は2重の安全機構があるとは言え、打針を通す穴が弾頭から雷管まで一直線につながっており、打針には常に雷管を叩く方向の加速度が加わるから、安全栓の回りにささいな組立ミスや公差外れなどがあると、異常作動を起こして一挙に自爆する可能性を内在している点であった。この腔発がひとたび発生すれば銃身は破裂し、零戦であれば片翼は吹き飛び墜落の憂き目を見ることになる。
初期の国産20ミリ機銃はこの腔発に悩まされ、99式20ミリ1号固定機銃2型と2型改1の銃身を強化して腔発の外部への影響を少しでも少なくするため、銃身に鋼線を巻き付けた2型特と2型改1特をわざわざ制式化している程である。
ローター式信管の開発
初期の機械式弾頭信管の欠点を改善したのがローター式信管である。安全栓をパチンコ玉に穴が開いたような形をした転輪(ローター)に換え、弾丸が回転するとローターが遠心力で回転し、ローターに開いた穴が打針と一直線になる仕組であった。
このローターが遠心力で回転しない限り、絶対に打針が雷管を叩けない仕組である。現代の信管も小型の機械信管は基本的にこの型式を踏襲する優秀な機構である。このローター式信管は99式20ミリ機銃信管2型と名付けられ、この信管付の弾薬包は以下の5種類が造られた。
通常弾弾薬包改2(識別色/錆色白線2本)
曳跟通常弾薬包改3(識別色/赤・白線3本)
曳跟通常弾薬包改4(識別色/赤・太白線1本)
改3は曳跟色が赤、改4は曳跟色橙または黄
焼夷通常弾薬包改3(識別色/黄・白線3本)
焼夷通常弾薬包改4(識別色/黄・太白線3本)
改4は焼夷剤の黄燐の安全性改善した弾薬。
通常弾用信管と曳跟通常弾用信管の違い
曳跟通常弾用信管は敵に命中しないと自爆する。この機能は通常弾用信管にはない機能である。曳跟通常弾用信管には最底部にの雷管の底に穴が開いている。
曳跟が尽きるまで敵に当たらないと、雷管底部のこの穴から曳跟の火が炸薬を伝わって信管に伝わり、自爆するのである。